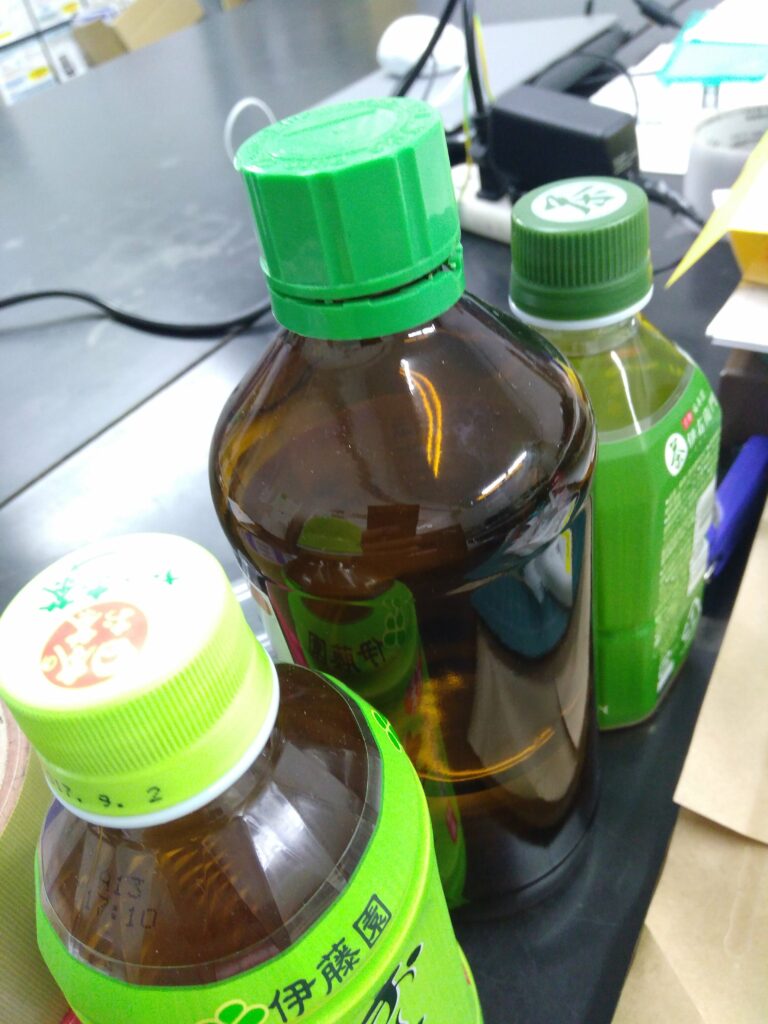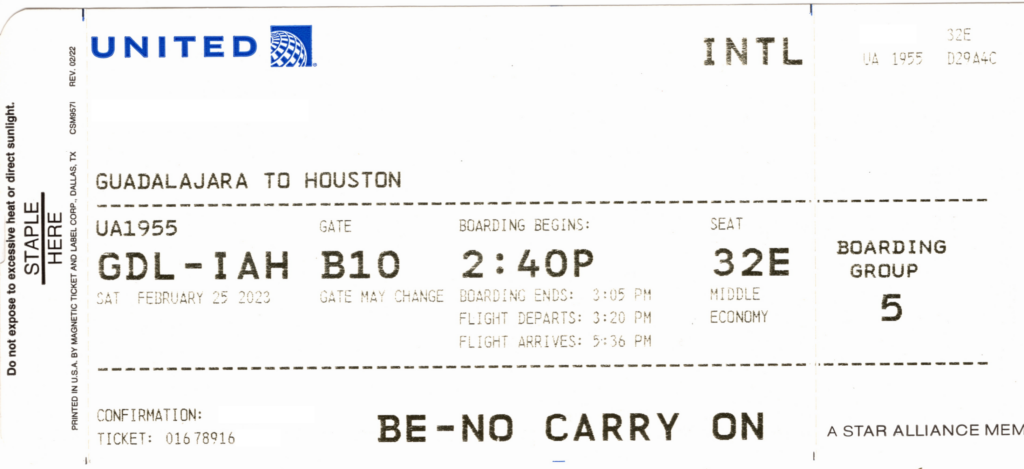報道各社および外務省からの情報によれば、2024年12月1日、ベラルーシ共和国南東部のホメリ州にて鉄道写真を撮影していた男性が、スパイ行為の容疑で現地の警察に拘束され、その後КГБ(Комитет государственной безопасности *¹、ベラルーシの情報当局)に逮捕されたとのことです。
ホメリ州においては、2024年9月にも邦人の日本語教師がスパイ容疑で逮捕されています。なお、ホメリ州はロシア連邦による武力侵攻を受けて戦争状態にあるウクライナと国境を接しています。
ベラルーシ共和国とウクライナの関係は、直接の交戦がないとはいえ、ベラルーシ共和国がロシア連邦に対して兵站(ロジスティクス)面で支援をしていることから、敵対関係にあると評価することができます。
このような中で渡航を決断することの危険性は周知のことと思われますが、鉄道・港湾施設・空港施設などのインフラ施設の写真撮影自体が極めて危険であるという点には留意すべきです。
当社においては、東欧地域に設置されたデータセンタ施設の安全性評価のため各種情報を収集しているところですが、ベラルーシ共和国の鉄道系労働組合にあたるСЖБ(Сообщество железнодорожников Беларуси、ベラルーシ鉄道労働者組合)のウェブサイトに掲載された事案の概要における記述には特に注目しています。
что так называемая «охота на ведьм», начатая на БЖД более 4 лет назад, не прекращалась ни на минут и продолжается по настоящее время. В подтверждение этому может служить сулимая руководством БЖД награда «за голову» выявленного гипотетического «шпиона» или «диверсанта».
すなわち、スパイ行為を通報した列車の運転士の動機は「小遣い稼ぎ」のためだという主張です。СЖБが反体制派の労働組合であることには留意が必要ですが、旧ソ連の地域においてはさほど珍しいケースではありません。
このようなトラブルがしばしば発生する地域としては、ベラルーシのほか、ロシア連邦、カザフスタン共和国、クルグズスタン(キルギス共和国)およびラトビア共和国が挙げられます。
ラトビア共和国は、現在では西側諸国とされていますが、ロシア連邦による侵略を現実の脅威として認識しており、鉄道写真の撮影が規制されています。欧米人やアジア人であっても逮捕されるケースは多いとされています。
他方、東側諸国や旧東側諸国でも、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、モンゴル国やウズベキスタン共和国では鉄道写真の撮影からトラブルに発展することは稀であるとの認識を有しています。
政情不安の地域に渡航する際、ましてやインフラ施設を撮影する際には、こうした状況をよく認識したうえで、自らがСпионの嫌疑を晴らすだけの言語能力を有しているか確認するべきでしょう。0でなければ100だというのが旧ソ連の常識です。
*¹ ベラルーシ語ではКДБ(Камітэт дзяржаўнай бяспекі)